ビジネスを取り巻く外的環境の変化が激しい中、経験やスキルなど即戦力を求めて、中途採用に力を入れようとしている企業も多いのではないでしょうか?
変化が続き様々な対応が求められる現代において、優秀な人材を確保することは企業にとって成長の鍵とも言えるでしょう。
しかし、中途採用を行っている企業の中には、「せっかく優秀な人材を採用したにもかかわらず、すぐに辞めてしまった」「企業風土に馴染まず、本来の力を発揮するのに時間が掛かった」などの悩みの声を聞くことも多いです。
約20年間にわたって企業の採用ブランディングに携わってきた私たちパラドックスは、企業の中途採用においても「スキルフィットだけでなく、企業のミッション・ビジョンに共感できるカルチャーフィットした中途採用を心がけること」が大切であると考えています。
今回は、中途採用の基本知識からメリット・デメリット、そして中途採用を成功させる考え方について、私たちパラドックスの考え方を交えながらご紹介します。
中途採用のミスマッチなどに悩む経営者や担当者の方にとって、この内容が悩み解決のヒントにつながると幸いです。
1:中途採用とは
そもそも新卒採用以外で不定期に行う人材採用や就業経験がある人を採用することを「中途採用」と言います。
中途採用は、採用に決まった時期はなく、企業が事業戦略に合わせて、人材の補強を必要とするタイミングで募集する点が特徴です。
1-1:中途採用と新卒採用の違い
新卒採用と中途採用の大きな違いは、求職者の「就業経験」の有無です。新卒採用は、その年に学校を卒業する人が対象となり、年齢制限などはありません。
アルバイト経験は例外になりますが、基本的には学校を卒業してから初めて社会で働く人のことを指します。
中途採用と新卒採用の違いを表にまとめましたので、見ていきましょう。
| 中途採用 | 新卒採用 | |
| 採用対象 | 就業経験あり | 就業経験なし |
| 採用基準 | スキル重視 | ポテンシャル採用 |
| 採用時期 | 不定期 | 一括採用 |
中途採用はすでにスキルや経験を身につけた即戦力人材、スペシャリストや管理職などの経営人材を採用するケースも多いです。
近年では、新卒入社3年以内で転職する人材も増えているため、中途採用であってもポテンシャル重視で若手人材を積極的に採用している企業も増えています。
2:企業にとって中途採用を行うメリット
中途採用と新卒採用の違いについて理解できたところで、続いては企業が中途採用を行うメリットについて見ていきましょう。
2-1:即戦力を確保できる
中途採用の大きなメリットの一つとして、「即戦力を確保できる」ことが挙げられます。
新卒採用とは異なり、中途採用では経験豊富な人材を採用できます。そのため、中途採用を行う際には職種別に採用することが一般的であり、必要な経験やスキル、資格を明示して採用活動を行う企業が多いでしょう。
募集から選考、内定までにかかる時間は2〜3週間ほどであり、一般的に1〜3ヶ月の引き継ぎ期間があれば、現職での引き継ぎを済ませての、入社が可能です。
しかし、優秀な人材ほど、現在の働いている企業でも重要なポジションを担っているケースも多いので、面接をしてみて、どうしても必要な人材であれば、実際の入社までの期間に余裕を持って提示することも大切になってきます。
自社では得られないスキルや経験を持った人材に出会えることが中途採用の良さでしょう。
2-2:研修の時間と費用が抑えられる
新卒採用の場合は、社会人としての基本的なビジネスマナーから業界に関する知識、経験など、実務に慣れるまでに研修などを実施する企業が多いでしょう。
中途採用の場合はすでに社会人経験があるため、新卒よりもある程度の基本知識を持っている方が多いです。
また、同じ業種で働いていた人を採用できれば、すでに業界のことを知っているため基本的な研修にかかるコストなども削減できます。
社会人としても基本的な知識を備えた中途採用者であれば、育成にかかる研修の時間と費用が抑えられるので、企業側にとってもメリットが大きいと言えるでしょう。
2-3:入社時期が調整できる
新卒採用とは異なり、中途採用は1年中どのタイミングでも募集を出すことができます。
欠員補充や既存事業の拡大、新規事業の立ち上げなど必要な時期に募集をかけることができるので、入社時期の調整が可能です。
また、募集から内定まで数週間ほどと採用プロセスも短縮化できるため、新卒採用とは違って随時入社してもらうことができることもメリットでしょう。
2-4:今まで培われてきた知識やノウハウが活用できる
今までの経験で培った知識やノウハウを自社に展開してもらえることも、企業側にとっては中途採用の大きなメリットです。
同じ業界で活躍していた人材を獲得することができれば、自社になかった知識やノウハウを取り込むことが可能になり、人材の多様性が生まれ、さらなる企業の成長や発展につながるでしょう。
また、知識やノウハウ以外にも、中途採用者が築いてきた人脈を獲得できるケースもあり、新たな販路獲得などのチャンスもあります。
すでに働いているメンバーにとっても、中途採用者の新たな知識やノウハウは刺激となり、今までのやり方をブラッシュアップする機会にもなり、組織の活性化につながるかもしれません。
3:企業にとって中途採用を行うデメリット
企業にとってもメリットが大きい中途採用ですが、一方でデメリットもあります。続いては、企業にとって中途採用を行うデメリットについて見ていきましょう。
3-1:すぐに辞めてしまう可能性がある
何度か転職経験がある人は、採用されても数年で辞めてしまう可能性もあります。
好奇心が旺盛で様々なことにチャレンジしたいという志向性は、裏を返せば、熱しやすく冷めやすいと言えるかもしれません。より挑戦できる案件やより条件がいい企業と出会えば、再び転職をする可能性は高いといえます。
企業側が長期的な視点で、将来のポジションやキャリアイメージを伝えて採用しても、本人は別のライフプランを計画している場合もあるでしょう。
中途とはいえ、面接でお互いのビジョンや時間軸を確認し、働き方をすり合わせていけるかが重要になってきます。
3-2:自分のやり方に固執される可能性がある
新卒採用の場合は、一から企業文化を教育できますが、中途採用の場合は馴染みきれない可能性があります。
中途採用者は今までの経験や培ってきたノウハウなど、自分のやり方に固執してしまい、新しい会社の企業文化に沿った方法を学ぶまでに時間がかかることもあり得えます。
新しい社風や考えに馴染めず、自分のやり方に固執してしまっては、他社では優秀な人材であっても、新しい環境では即戦力にならないケースもあるのです。
頭ではわかっていてもいざ働いてみると、どうしても昔のやり方や考え方が抜けず、苦労をしている中途入社の方もよくお見かけします。中途入社だから、入社したら手をかけないで大丈夫ということではなく、入社から定着までのオンボーディングと言われる期間での手厚いサポートも大切です。
本人の努力はもちろんですが、受け入れる企業側の長期的な視点やサポートも欠かすことはできません。
3-3:企業文化が育たない
中途採用は経験豊富な即戦力を採用できるメリットがありますが、一方では若い世代が採用されず、企業としてのカルチャーを担う人材が育たない可能性があります。
もちろん人にもよるのですが、ある程度経験を積んだ中途人材は、0から新卒人材を育てた経験が少なく、教えることに慣れていないケースもあります。一長一短あるとは思いますが、企業独自の文化を次の後輩に教えていく意識も、新卒文化が強い企業に比べて弱いかもしれません。
即戦力重視の採用を続けていくうちに、気づいたら企業の中核をなす若い世代がおらず、組織の高齢化と空洞化に繋がってしまうケースもあるため、バランスを考えて採用を行うことが重要です。
4:中途採用を成功させる考え方
ここまで中途採用のメリット・デメリットについてご紹介してきましたが、「優秀な人材に長く働き続けてほしい」と考える経営者や採用担当者も多いでしょう。
いくら即戦力が欲しいからとは言え、スキル重視だけの採用では、ミスマッチによりすぐに離職してしまうケースも考えられます。
ここでは、約20年にわたり企業の採用に携わってきた私たちパラドックスが考える「中途採用を成功させる考え方」について見ていきましょう。
4-1:採用目的を明確にする
当たり前ですが、中途採用を始める前に必ず、なぜ中途採用を行うかという目的を明確にしましょう。
どのような事業課題や組織課題があり、その解決のためにどのようなキャリアとスキルを持った人材をどのタイミングで、どのくらい、どのような報酬で採用したいのかを、経営・人事・現場で共有しておきましょう。
実際に中途採用を始めてみると、もともと想定をしていた人材要件とは異なるのですが、優秀な人材に出会うことも多々あります。その際に、条件反射的に採用してしまうのではなく、当初の目的からは外れますが、それでも採りに行くべき人材であるかなど、議論ができるだけの情報の土台づくりができているのがベストです。
4-2:採用ターゲットを明確にする
次に、「どのような人材を採用したいのか」を明確にしていきましょう。
採用ターゲットを明確にすることで、求人掲載で打ち出すポイントが明確になり、アンマッチを防ぐことにつながります。
中途採用者に求めるスキルや経験値、資格などのスキルセットと価値観、志向性などのカルチャーフィットの視点から採用要件を決めましょう。
スキルセットに関しては、現場のニーズをヒアリングしながら洗い出し、下記の2つの視点から精査することが大切です。
- MUST条件(絶対に外せない採用条件)
- WANT条件(備わっていれば良い採用条件)
また、カルチャーフィットとは、自社の企業文化への適応性のことであり、軽視してしまうと、採用後に職場に馴染めなかったり、能力を発揮できず早期離職にも繋がってしまいます。
4-3:採用コンセプトを設定する
採用ターゲットが明確になったら、次は採用コンセプトを設定しましょう。
採用コンセプトとは、一言で表すと「採用活動における指針」のことです。企業がどんな人を採りたいのか、どんな企業文化なのか、が伝わるものであるため、企業のリクルーターや面接を行うメンバーに伝える際にも必要になります。
新卒採用では、採用コンセプトをつくることは当たり前になりつつありますが、中途採用ではまだまだ一般的ではないかもしれません。
しかし、企業にとっての中途採用のニーズが高まり、エンジニア採用のように多くの企業が年間を通じて中途採用を行うような現在では、やはりコミュニケーションの起点としての中途採用コンセプトは必要になってきているように思います
採用コンセプトを作る上で重要な3カ条は、下記の通りです。
“採用コンセプトの3か条”
- 企業理念と紐づいていること
- 大切にする価値観が伝えられていること
- ターゲットの共感を得るものになっていること
***採用コンセプトについて詳しく知りたい方はこちらの記事へ!
採用コンセプトづくりにおいては、企業理念と紐づき、大切にする価値観をしっかり伝えられていることが大切になります。企業と転職者のマッチングにはお互いの価値観が非常に重要になるためです。
また、ターゲットから見てどのような企業に映るかを考え、そこに寄り添い共感を得られることが大切になります。
4-4:ミッション・ビジョンの要素が内包された採用基準を設定する
採用コンセプトが設定できたら、次に採用基準を設定しましょう。
一般的には、「スキル」「学歴」などの尺度のみが基準となっている企業が多いですが、このような採用基準しかない場合は改めて検討されることをおすすめします。
もちろん、スキルなども重要な要素の一つですが、採用基準で大切なことは「その企業の志やミッション・ビジョンといった要素が内包されたユニークな基準」を入れることです。
企業のミッション・ビジョンに沿ったユニークな採用基準を設けることで、採用フローやイベントなどの企画にもエッジが効いて、「企業らしさ」を体現することができます。
その企業ならでは、企業らしさの伝え方に悩む企業は、ユニークな採用基準から考えてみることも一つの方法です。
4-5:内定理由を明確にする
そして、中途採用における最後の重要なステップは、「内定理由を明確に伝えること」です。
内定理由をしっかり伝えられることで、ただ内定をもらう場合と大きな差が生まれます。
内定理由を伝える際は、先ほどの「採用基準」と紐づけて伝えることがポイントです。採用基準が明確でユニークであるほど、内定理由もユニークなものになり、他社では言われないオリジナルな理由として相手に届けることができるでしょう。
内定理由を明確に伝えることで、「この会社なら自分の長所が活かせそうだ」といったように内定承諾の可能性も高まります。
5:まとめ
今回は、中途採用のメリット・デメリット、そして私たちパラドックスの考えを交えながら中途採用を成功させるための考え方をご紹介しました。
中途採用は即戦力となる人材と出会えるメリットだけではなく、ミスマッチにより離職などのデメリットもあります。
「スキルを持った優秀な人材が欲しい」と希望される企業も多いですが、転職者と良い関係を築くためには、スキルフィットだけでなく、企業のミッション・ビジョンに共感できるカルチャーフィットした中途採用を心がけることが大切です。
この内容が中途採用に携わる経営者や人事担当者にとって、課題解決のヒントになると幸いです。
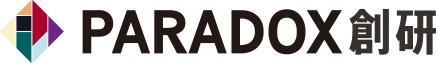



コメント